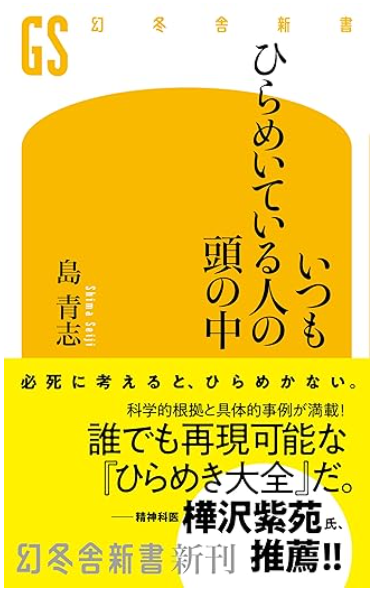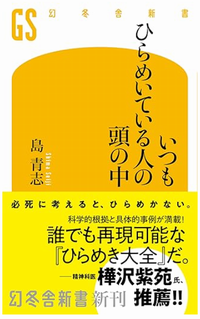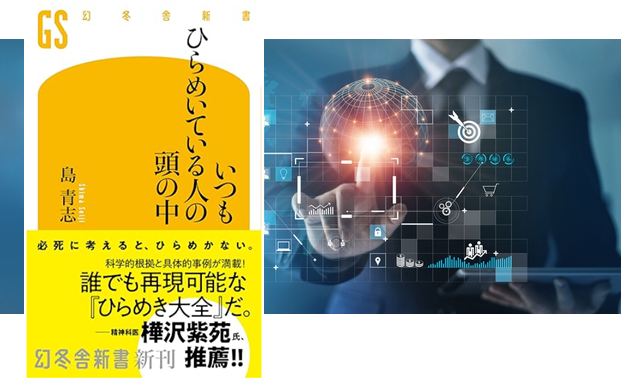
誰もが「ひらめく」ことができる
一つの「ひらめき」が自分の人生を変える。あるいは世界を変える。
世界を変えた起業家たちのようなビジネス(あるいは他のこと)を生み出して、誰もが認める成功者になる。
これは彼らが特別に選ばれた人だからできたことで、私たちには絶対無理だと思っていませんか?
もちろん誰もが「世界を変えるような成功者になることができる」などと言うつもりはありません。スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツになるには、人並み外れた努力や運が欠かせないだろうと私も思います。
ただ一つ言えるのは、彼らのように「ひらめき」や「創造性」でビジネスのアイデアを見つけることや、人生を変えることは、誰もが可能であるということです。
「神様は、金持ちにも貧乏人にも1日24時間という時間だけは平等に与えてくれた」という表現がありますよね。私はそれに「ひらめき」「創造性」を加えたいと思います。
多くの人は(その気になれば)努力は自分にでもできると考えていますし、日曜日の競馬場の混雑や、年末の宝くじ売り場の行列を見れば、運だって自分に降ってくるかもしれないと期待しているのもわかります。
でも、ひらめきや創造性は自分には無縁だと思っている。こういうのは特別に選ばれた才能あふれる人だけのものだと思っているかもしれません。
なぜならひらめきも創造力も、私たちに備わっている基本的な機能だからです。
私たちは今からおよそ40億年前に、原始の海で生まれて以来、創造と進化を続けてきました。この長い進化の過程で、創造という力は私たちの遺伝子に組み込まれています。創造する力やひらめく力は、特別な才能ではなく、むしろ私たちにとって当たり前のものなのです。
創造性やひらめきがどのように生まれるのか、そのメカニズムは100年以上にわたる研究で徐々に明らかになってきています。このメカニズムを理解することで、誰でもひらめきを感じ、創造力を発揮できるようになるでしょう。
100年前にポアンカレが明らかにした「ひらめき」のプロセス
三体問題やポアンカレ予想など、数々の数学的発見を行ったことで知られる数学者のアンリ・ポアンカレは、1908年に刊行された「科学と方法」(日本語版:岩波文庫)の中で、ひらめきや創造性というのは、「知の美しい組み合わせかた」であると述べています。
私たちが新しいアイデアを生み出したり、新しい発見を行ったりするのは、何もないところから生み出しているのではなく、私たちが今まで蓄えてきた(インプットされた)知識を、脳が最適なかたちで組み合わせることにより、新しいアイデアや発見という形でアウトプットがなされています。
ここでいう「最適なかたち」を脳がどのように判断しているかというと、これが「美意識」であるとポアンカレは述べたのです。
このポアンカレが述べた内容は、前に述べた囲碁や将棋の話とも同じです。
陣形が最も美しくなるような場所に、棋士が石や駒を置くように、数学の知識の断片が、頭の中で美しく配置されたときが、新たな数学的発見が行われたときである。これは、ジグゾーパズルを思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。
あなたの頭の中には、例えばこの図のような無数のピース(知識の断片)があります。

このような16ピースのパズルでも、20兆通りの組み合わせがあります。これを片っ端から試そうとしたら、1パターンを1秒としても60万年以上かかります。
でも実際には、私たちは数分もあれば、このパズルを解けるのではないでしょうか。
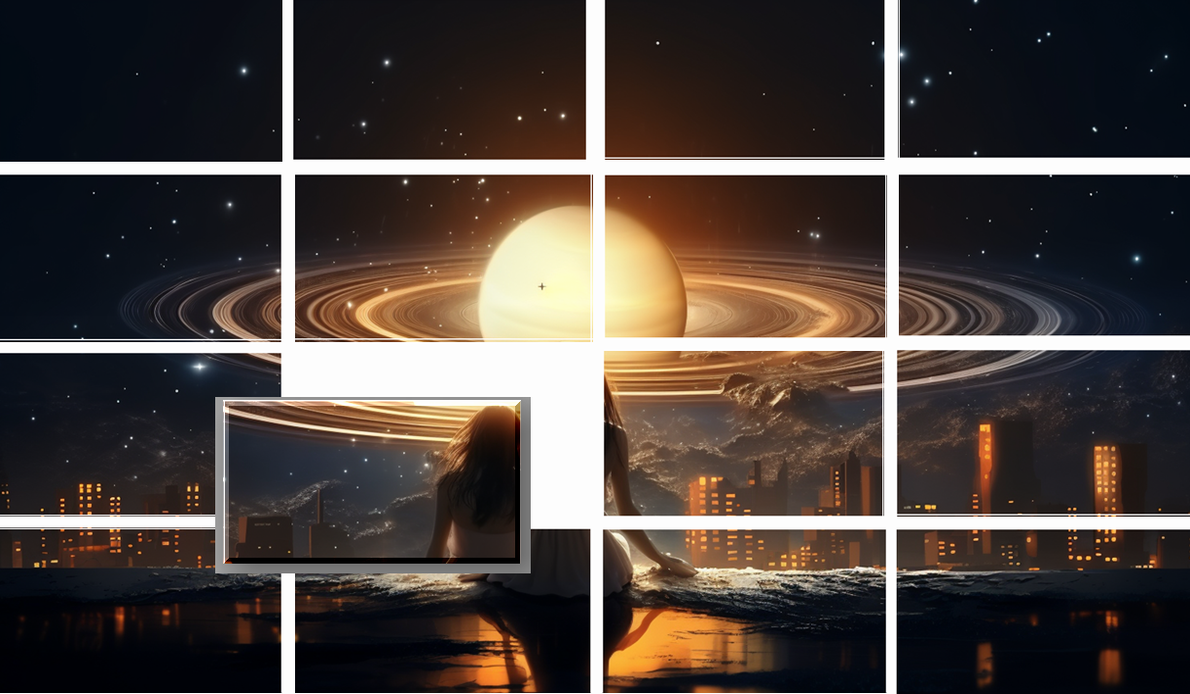
このパズルは、全部同じ長方形ですので、私たちはその絵を見ながら、どう並べれば最も美しく見えるかという基準でピースを置く場所を選んでいるはずです。
間違ったピースを使ったり、ピースを間違った場所に置いたりすれば、美しいものにはなりません。
ジグゾーパズルの最後のピースが埋まって美しい絵が完成したときが、まさに「ひらめき」の瞬間であり、そのピースがはめ込まれた「カチッ」という音が「ひらめきの音」なのです。

そして、この完成した絵が正しいかどうか、実際のものと比較したり、まわりの人に見てもらったりなどの方法で検証します。
これが、ポアンカレが考えた「ひらめき」の流れです。
繰り返すと、まず必要なピースを集める準備の段階がある。囲碁や将棋のルールを覚えたり、数学の知識を学んだり、練習や経験を積む段階です。
そしてそのピースを組み合わせる段階。卵の中で最初はどろどろの状態だったものが、だんだんひな鳥を形成していくような孵化の段階。私たちはここで「美」を手がかりにピースの場所を定めます。そして最後の1枚が正しく嵌まるひらめきの段階。最後にそれが本当に正しいか検証をする段階があります。
1908年の「科学と方法」の中でポアンカレは、ひらめきや創造は、この「準備」「孵化」「ひらめき」「検証」というプロセスで行われると述べました。
このポアンカレの考えは、その後1937年、コロンビア大学のキャサリン・パトリックが100人のアーティストを集めて行った実験で検証され、アーティストが創造的な活動を行う際にも、この4つのプロセスを踏んでいることが示されました。
また米国の大手広告会社の重役で、The Ad Council(日本の公共広告機構(AC)が見本にした団体)の初代会長を務めたジェームズ・ヤングは、1940年にポアンカレのプロセスを基に「アイデアのつくり方」(日本語版:CCCメディアハウス)という小冊子を出版して、これは日米で現在も版を重ねているロングセラーとなっています。