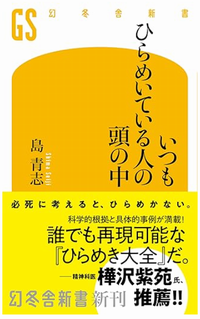振り返り(レトロスペクティブ)を制すものアジャイルを制す
アジャイル(特にスクラム)への注目が高まっていて、弊社にも相談やコンサルティング依頼もいただいています。
アジャイルのコンサルティングをする際、「導入スケジュール」をつくったり、どのプラクティスから導入していくかアドバイスしたりします。どのようなアプローチをするかは、もちろん会社や組織の状況によって異なりますが、これからアジャイルを始めるという組織の場合、私たちはまず「振り返り(レトロスペクティブ)」から始めることをお勧めするケースが多いです。
アジャイル開発やスクラムの本を読むと、当然のことながらその説明は時系列順に書かれています。確かに1からメンバーを集めて新たなプロジェクトをスタートさせる、という状況では当然チームの役割を決めたり、アジャイルの仕事の進め方を定めていく事から始めます。こういうときは「頭から始める」という形になるでしょう。
しかし、私たちが担当したアジャイルのプロジェクトでは多くの場合、既にあるチームや既に進んでいるプロジェクトがある、あるいはその両方がある状況で、仕事のやり方をアジャイルに変える、というケースが大半を占めます。
そのような場合でも、まずプロダクトオーナーやスクラムマスターを決めたり、バックログをつくるなど「スクラムガイド」などに書かれている順に取り組もうとしますが、なかなかうまく定着しないという結果になっていることが多い印象を受けます。
そのようなケースでは、プロジェクトの進行もスムーズいかないので、時間の余裕がないことを理由に「振り返り(レトロスペクティブ)」を行わない、行ったとしても形だけになってしまう。
また、プロジェクトがうまくいかない中で「振り返り」を行うと、振り返りが「反省会」のようになってしまったり、あるいは個人の失敗を指摘する場、リーダーへの不満を言う場のようになってしまっているケースもありました。
これでは、アジャイル(スクラム)の基本であるスプリント(イテレーション)をうまく回すことができません。
なぜならスクラムに限らず、アジャイルはフィードバックによって現在の位置や状況を把握しながら自律的に進めていくものだからです。
スクラムの様々なプラクティス、カンバンボードやデイリースタンドアップ、バーンダウンチャート等の目的も同様に、メンバー一人ひとりが現状を把握するためのものですし、ユーザーストーリーやバックログをつくって、細かくタスク管理を行っているのも、フィードバック管理がやりやすくなる為です。
XP(エクストリームプログラミング)の手法で挙げられている「ペアプログラミング」もペアとなるプログラマーがフィードバックしあうことで、ミスによる手戻りをなくし仕様を共有できる仕掛けと言えます。
このようにアジャイル(スクラム)は、フィードバック管理がすべてといっても過言ではないメソッドです。このフィードバック管理の一番の要(かなめ)が、スプリント(イテレーション)という一番の根幹をフィードバックする「振り返り(レトロスペクティブ)」なのです。
つまり「振り返り(レトロスペクティブ)を制すものアジャイルを制す」といっても過言ではないのですね。
その上、「振り返り」はアジャイルだけでなく、今までのウォーターフォール的な仕事の進め方であっても有効なプラクティスです。
仮にアジャイルへの移行を取りやめて、「振り返り」だけ行っても、業務の効率化やチームの一体感醸成に大きな貢献をしてくれる筈です。

アジャイル(スクラム)の流れ
「振り返り(レトロスペクティブ)」は「反省会」ではない
「振り返り」を導入するにあたって、一番留意したいのが、「振り返り(レトロスペクティブ)は反省会ではない」という点です。
実際にはアジャイル(スクラム)の「振り返り(レトロスペクティブ)」を「反省会」のように捉えている人やチームは結構見受けられます。
確かに振り返りの際、スプリントの過程でうまくいかなかったことを振り返って、次に活かすのは大事なことですが、上述のように、「振り返り」は誰かを責めたりする場ではなく、チームの現在地を正しく全員が把握する場です。
今いる位置を確認し、ゴールや目的までどのように進路をとるか全員の意思統一をするのが「振り返り(レトロスペクティブ)」の目的です。
「振り返り(レトロスペクティブ)」は、ホワイトボードを囲んで行う
「振り返り(レトロスペクティブ)」がうまくいくコツをここで述べましょう。
それは、ホワイトボードを囲んで話し合いをするということです。
おそらく通常の会議においてもホワイトボードを使用することは多いと思いますが、その役割は、議事録として後に残すことであったり、皆に共有したい内容を示すことだったりすると思います。
「振り返り」でももちろんその為にも使用しますが、もっと重要なホワイトボードの機能は、「お互いの顔を観ながら直接議論するのではなく、ホワイトボードを介してディスカッションをする」ことにあります。
通常の会議ですと、リーダーや司会が上席に座る下図左のような形になることが多いでしょう。このやり方はお互いの顔を見ながら対話する形式です。
このやり方で、「スプリントの間うまくいかなかったこと」「改善したいこと」を議論すると、どうしても「誰々のやり方が良くなかった」という形になりがちです。
また、改善策やアイデアなどを話し合う場合でも、出された意見は「誰が言った意見なのか」ということに紐づけされるので、声が大きかったり、権力のある人の意見が重み付けられるのは避けられません。

しかし右のように皆がホワイトボードに向き合い、そこで描かれていることや付箋などを見ながら議論すると「人」ではなく、「物事」つまりプロセスやシステム、やり方について話し合いができるようになります。
一見些細な違いに見えますが、プロジェクトの結果を左右するほど大事なことです。
オンライン会議の場合も同様で、Miroなどのオンラインホワイトボードを全員で使いながらディスカッションしましょう。
「振り返り(レトロスペクティブ)」は「失敗した人に反省を促す場」ではなく、「うまくいくためのプロセスや仕組み、やり方の改善を行う場」です。
そして「振り返り」を自分たちでできるようになるということは、アジャイルに必要なマインド、フィードバックに対する心構えができてきたということです。これは上述のように、アジャイルのあらゆる手法やプラクティスのベースとなるマインドを身に着けたということです。
「振り返り」を身につけた後、アジャイルの他のプラクティスに取り掛かると、とてもスムーズに移行できることに気がつくと思います。
日本能率協会主催「DX時代に求められる「3つの思考法」入門セミナー」開催