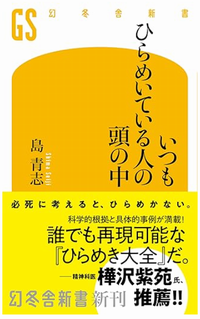アジャイル・ガバナンスとDXは表裏一体の関係
アジャイル・ガバナンスについて、こちらのページで自分なりの解説記事を書きましたが、Society5.0社会にむけて、政府、企業などが行うガバナンス(統治・経営)の新しい形(アーキテクチャ)が今注目されています。
経済産業省による報告書「Governance Innovation vol.2-アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて-」では、「政府、企業、個人・コミュニティといった様々なステークホルダーが、自らの置かれた社会的状況を継続的に分析し、目指すゴールを設定した上で、それを実現するためのシステムや法規制、市場、インフラといった様々なガバナンスシステムをデザインし、その結果を対話に基づき継続的に評価し改善していくモデル」とされています。
この「アジャイル・ガバナンス原則」は、昨年12月に閣議決定された「デジタル社会に向けた構造改革の5つの原則」のひとつですが、下図のようにこの「5つの原則」はそれぞれが重層的に折り重なっていて、第5層にあたる「アジャイル・ガバナンス原則」は、その上(第6層)の「デジタル完結・自動化原則」、さらには目的である構造改革、新たな価値の創出を支えるものであることがわかります。

デジタル社会に向けた構造改革の5つの原則
「デジタルによる構造改革を行い、新たな価値を創出する」とはまさにDX(デジタル・トランスフォーメーション)のことです。つまりは、アジャイル・ガバナンスとDXは表裏一体、セットで考えなければなりませんし、DXの実現のためには、アジャイル・ガバナンスが欠かせないことになります。
DXにアジャイルが必要なわけ
DXにアジャイルが欠かせない、それも単にシステム開発にスクラムなどのアジャイル開発の手法を使えば済むというレベルではなく、組織全体としてアジャイルな体制が必要であることは、経産省による2018年の「DXレポート」でも強調されていたことでした。
なぜなら、コロナ禍を省みるまでもなく、先が見えない激変する経営環境の中で、長期計画や年間計画を立てても、期が終わる頃の状態を完全に見通すことは、どんな有能な経営者でも不可能だからです。
環境や状況の変化に合わせて、柔軟に体系を組み替えることは、システムだけでなく、営業や経営にも必要です。今までのPDCAやウォーターフォールのように期首に定めたことを変えず、期中には計画をどのくらい達成しているかだけを見ればよかった時代から、今は大胆そして柔軟(Agility)に期首計画そのものを絶えず見直していくことが、企業や組織の生き残りに欠かせません。
そして変化する環境に自分を合わせるばかりでなく、その中で新たな価値を創っていくことができる組織へと転換(トランスフォーム)していく。これがDX(デジタル・トランスフォーメーション)です。
アジャイル・ガバナンスの報告書でも「『予め一定のルールや手順を設定しておき、それに従うことでガバナンスの目的が達成される』というガバナンスモデルは困難に直面することになる。Society5.0では、このようなモデルに代わり、一定の「ゴール」をステークホルダーで共有し、そのゴールに向けて、柔軟かつ臨機応変なガバナンスを行っていくというアプローチが重要になると考えられる。」と記されています。
アジャイル・ガバナンスのデザイン
アジャイル・ガバナンスを実践するため、報告書では「アジャイル・ガバナンスの基本コンポーネント」を示しています。

「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」「改善」といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていくガバナンスモデルです。
そしてアジャイル・ガバナンスはガバナンス(統治・経営)という言葉から、政府や一部の経営者だけの問題であって、ほとんどの人には関係ないというイメージを持たれがちですが、この対象は、政府や企業ばかりでなく、市場、個人やコミュニティなどにも及びます。
それぞれが、協働して行うガバナンスのイメージが下図です。
これは重層的にシステムが折り重なるSystem of Systemsからのアナロジーで、「ガバナンス・オブ・ガバナンス」と名付けられていますが、コロナ禍の初期の段階で、政府、市民間の情報システムを短期間で創り上げたオードリー・タン大臣らの活躍で知られる台湾では「協働ガバナンス」と言われているそうで、こちらのほうがイメージの湧きやすい言葉かもしれません。

ガバナンス・オブ・ガバナンス(マルチステークホルダーによる協働ガバナンス)
アジャイル・ガバナンスの実装フレームワーク
このようにDX推進に欠かせない、アジャイル・ガバナンスを企業や組織が導入するためには、マインドを組織に浸透させることや、上図のアジャイル・ガバナンス・サイクルのプロセスを理解することも大事ですが、具体的な実装フレームワークや手法を使って「アジャイル・ガバナンスを実装すること」が大事です。
それも、アジャイル・ガバナンスとDX戦略を両方同時に進めることです。
もちろん、「アジャイル」ですから、社長が朝礼か何かで、「今日からアジャイル・ガバナンスに変える」というのは馴染めません。(もちろんマインドを変えるという意味で「宣言」すること自体は悪くないかもしれませんが・・・)
「アジャイル・ガバナンス」自体アジャイルで少しずつ変えていくのが大事だと思います。
フレームワークとしては、昨年論文でも発表した「ICONIX for Business Design」のやり方があります。
まず現状のエコシステムを可視化し、経営の方向性を見出した上で、経営環境(外部環境、内部環境)を分析して、変えるべきポイント(レバレッジポイント)を見つける。
その結果を設計(デザイン)に組み込むというサイクル(Agile ICONIXでは「ロバストネス分析」と呼ばれています。)を続けながら、マルチステークホルダーとどのように協働するか、CVCAを描いて協働や価値交換の形を描いていく。さらに時間軸に落とし込み、実装する。
鍵となるのは、協働の形を描くアート思考、まわりのステークホルダーと良い形を設計するデザイン思考、それを形にするシステム思考ですが、このフレームワークはそれぞれをまんべんなく取り入れているのも特徴です。
![]()
ICONIX for Business Design
日本能率協会主催「DX時代に求められる「3つの思考法」入門セミナー」開催