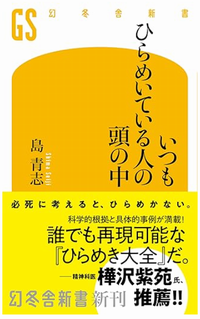アジャイル・ガバナンス原則
昨年末に政府が閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画(デジタル重点計画)」に盛り込まれた「デジタル原則」でも注目される「アジャイル・ガバナンス原則」。
もともとソフトウェアの構築手法であったアジャイル開発の手法は、システム全般のみならず、組織開発などガバナンスやビジネス全般に適用されるようになってきました。
これはもちろん、VUCAという言葉で著されるように、先の予測ができない時代、柔軟で敏捷な組織が必要とされることが共通認識となったからだと思います。
経済産業省による2021年の報告書「Governance Innovation Vol.2」では、「我々が目指すべきは、様々な社会システムにおいて、「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」「改善」といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていくガバナンスモデルであると考えられる。」と述べられています。
それぞれのプレーヤーが5つのプロセスに従いアジャイル・ガバナンス・サイクルを回し、ステークホルダー同士、お互いが協働しあう下図のようなイメージです。

アジャイル・ガバナンス・サイクルと協働ガバナンス(ガバナンス・オブ・ガバナンス)
Governance Innovation Vol.2(経済産業省 2021)
今までような、少数のトップが判断し下のものはそれに従うという社会から、政府、企業、個人、コミュニティや市場など、すべてのステークホルダーが自律的に協働する社会へ。
現在のDXブームやコロナ禍の混乱も含めて、社会に起こっている変化、この流れは止めることはできないし、あるいは逆に個人も企業もあるいは日本という国が取り残されてしまう。そういう時代なのだと思います。
アジャイルな組織とは

アジャイルな自律的ガバナンスは、1960年代の英国の炭鉱労働現場、QC活動などのカイゼンを現場手動で行った70年代の日本企業、アジャイルの業界で「スクラムの名付け親」とも呼ばれる野中郁次郎氏の研究などに遡ることができます。
今世紀に入ってからの動きとしては、スクラムのやり方を組織運営に適用させた「ホラクラシー」、リーンスタートアップや、個人の発達理論を組織論に適用した「ティール組織」が特に日本でブームになりました。
また、企業への自律組織導入も進み、米国のZapposは2015年に「ホラクラシー」を導入。またスウェーデンを拠点とする世界最大級の音楽配信会社のSpotifyも「アジャイル型組織」(Spotify Model)を導入しました。
Spotifyのアジャイル型組織は、Tribe(部族)Squad(分隊)Chapter(支部)などから構成されています。
基本単位がSquadで、これはスクラムチームと同じ機能を果たします。
Squadに分隊長のようなリーダはいませんが、プロダクトオーナーがプロジェクトの進捗などを管理します。またスクラムチームと同じく一つのSquadの中には多様な職種の人がいますが、その職種ごとの横断グループがChapterです。
Spotify Modelのようなアジャイル型組織は、大手金融グループのINGや、アクサグループ、ボッシュなどの大手企業を中心に導入が進められています。

Scaling Agile @ Spotify
Henrik Kniberg & Anders Ivarsson(2012)
既存組織をハックするアジャイルハック(アジリティハック)
このようなアジャイルの手法は、ビジネスの中でも特に機動力の高さが求められる領域で有効ですが、俊敏性よりも一貫性や効率性が求められる業務や部門の場合、効果がなかったり、また導入に困難が伴う場合があります。成熟産業の大量生産プロセスや、ルーティーン作業の業務や部署などのケースです。
ただしそのような産業の中でも、新たなプロジェクトの立ち上げなど非連続な変革が必要な場合もあります。
経営学者のデビッド・ティースは、「ダイナミック・ケイパビリティ」理論で、製造業においても環境や状況が激しく変化する中で、企業がその変化に対応して自己を変革する能力が必要であると述べています。
この能力(ケイパビリティ)は、感知(脅威や危機を感知する能力)、捕捉(機会を捉え、既存の資産・知識・技術を再構成して競争力を獲得する能力)、変容(競争力を持続可能なものにするために、組織全体を刷新し変容する能力)の3つを指しますが、これは、アジャイル・ガバナンス・サイクルの5つのプロセス「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」「改善」と同じ事を述べているのがお解りかと思います。
製造業のような、人よりも設備への投資が多い組織の場合は、既存の組織構造に手を入れるよりも、新たな別組織を立ち上げるほうが容易なケースが多いと思います。また場合によっては正式なアジャイルの手法ではない方法で打開している企業も見られます。
ハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソン、ランジェイ・グラティは、GE、ペプシコ、ソニーなどの事例を調査し、このような手法をアジャイルハック(アジリティハック)と名付けました。
アジャイルハックは、新規プロジェクトの立ち上げや、会社再生などのケースで有効とされます。
アジャイル組織の作りっぱなしでは効果はない
企業組織をアジャイルや自律する組織にしようとする場合、上記のような企業形態の事例は参考になると思います。
しかし、形、つまり組織形態だけ取り入れようとしても、おそらくうまくはいきません。
実際、ホラクラシーやティール組織、アジャイル型組織にしようと組織形態を変えてみたけれど、結局うまくいかなかったという事例は少なくありません。
アジャイルハックも、例えば「出島方式」で新たな組織を立ち上げたものの、事業の決裁や承認プロセスなどは今までと同じやり方のため、結局組織が煩雑になっただけというケースも耳にします。
形だけでなく、マインドやプロジェクトの設計手法、そして運用(オペレーション)の手法もしっかり定めていかない限り、うまくワークしないと思います。
アジャイル組織に必要なマインド
組織の形だけを変えても、経営者や働く人が今まで通り「計画は変えない」「決められたことを守る」というマインドのままでは、アジャイル型組織はうまくいきません。
いわゆるアジャイル思考 ― 「価値創造」「顧客志向」「変化への対応」― ができるかどうか。経営者自身もそうですし、今までのように期首に立てた目標の達成度で測るというような、評価制度も変えていかないと、社員も変わりません。
また個人的に面白いと思っているのが、「手放し経営ラボラトリー」がまとめたDXO「経営を進化させる実践書」に書かれているプログラムは、経営者やメンバーのマインドのプログラムとして役立つと思います。
アジャイル組織のためのプロジェクトのデザインと運用手法
アジャイル組織のためのマインドや組織形態、これはWhy(なぜ)、What(どのような)にあたります。そして実際に業務を進めていくためにはHow(どのように)、「どのように業務を遂行していくか」のデザインが必要です。
さらにこの「業務」は、「設計・開発」(デザイン)と「運営・オペレーション」に分けることができます。
今までの日本企業は、後者の「運営・オペレーション」に長けていると言われてきました。
前例を踏襲し、決められたことをきっちり守る。さらにはより効率的に仕事ができるようにカイゼンを行う。
これは社会の流れが遅かったり、かつての日本企業にとって当時の欧米企業のような「お手本」がある場合、威力を発揮しますが、現在のような変化が早く先が読めない時代は、前者の「設計・開発」(デザイン)も大事になります。
アジャイルなプロジェクトデザインの手法では、エンタープライズ・アジャイルのフレームワークとしてSAFeがあります。
SAFeは、大企業向けのアジャイル・フレームワークですが、もう少しコンパクトなアジャイル設計の手法として、ダグ・ローゼンバーグが開発したのがICONIXです。
ICONIXはソフトウェア・プロジェクト向けに設計されましたが、弊社ではビジネスデザインに適応させた「ICONIX for Business Design」を開発し、2021年日本ビジネスモデル学会誌で発表しました。
また、運用/オペレーションの手法では、アジャイル開発の、スクラム、カンバンなどがあります。
スクラムは、1週間~1ヶ月程度をひとつの期間(イテレーション/スプリント)として、フィードバックを行い、サイクルを高速で回しながら、変化する環境にも対応させることができるようになります。
![]()
ICONIX for Business Design

スクラムのオペレーション
日本能率協会主催「DX時代に求められる「3つの思考法」入門セミナー」開催