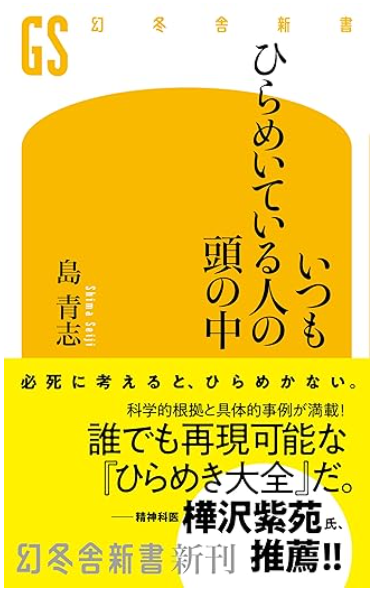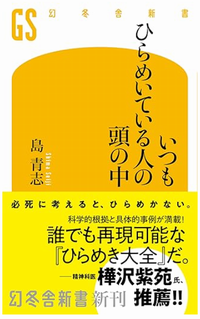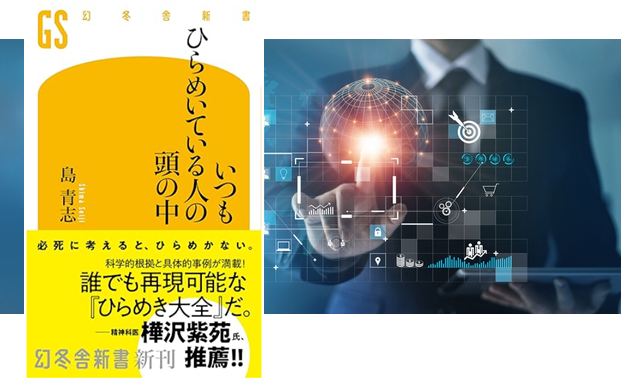
3月26日に「いつもひらめいている人の頭の中」(幻冬舎新書)を上梓しました。
この本は、このサイトのテーマであり、私たちが行っている企業研修やコンサルティングのベースでもある、アート思考、デザイン思考そしてシステム思考がベースになっています。
そしてその基盤の上に、創造性に関する最新の脳科学研究に関する説明を加えて、今回「新書」という誰もが親しみやすくこの考え方に触れられる形で、世に出すことができました。
事業創造やイノベーションを起こすために必要な、一人一人の「創造する力」を身につけるためにどういうことが必要なのか。
いつも研修やコンサルティングで語っているメソッドの、そのベースにあるものを著わすことができたと思います。
この本の出版に携わって頂いた幻冬舎の皆様には深く感謝申し上げます。
「ひらめき」「創造力」は誰もが平等に持つ能力
この本のポイント、そして私が最も訴えたかったことが、この記事のタイトルでもある「「ひらめき」「創造力」あるいは「イノベーションの力」は誰もが平等に持つ能力」であるということです。
自分のおでこに触ってみてください。今触れた皮膚の下、頭蓋骨の奥にあなたの脳があります。最先端のAIよりも遙かに複雑で高性能な機能を持った脳。今もおでこの奥で1000億近くのニューロンが、連携しながら発火し続けています。この仕組みを創ったのは、あなた自身です。
もちろん意識してではないでしょうし、また私たちはご両親やご先祖から受け継いだもの、そして毎日頂くたくさんの動植物の命によって今生きています。
それでも自分の脳を創り、成長させてきたのが「自分自身」であることに変わりはありません。
私たちは今からおよそ40億年前に、原始の海で生まれて以来、創造と進化を続けてきました。この長い進化の過程で、創造という力は私たちの遺伝子に組み込まれています。創造する力やひらめく力は、特別な才能ではなく、むしろ私たちにとって当たり前のものなのです。
創造性やひらめきがどのように生まれるのか、そのメカニズムは100年以上にわたる研究で徐々に明らかになってきています。このメカニズムを理解することで、誰でもひらめきを感じ、創造力を発揮できるようになるでしょう。

なぜ限界を感じてしまうのか
そうは言っても、「自分に創造力なんてない」「私は天才じゃないんだから、新しいアイデアを考えついたり、ひらめいたりできない」と思っている人は、意外に多いです。
そして同僚やライバル、あるいは誰かが「素晴らしいアイデアを発表して評価を受ける」「新しいビジネスモデルを創りだして成功する」のを見て、「・・自分にはあんな才能は無いからなぁ」と諦めた目で見てしまう。
その成功された方は、見えないところで誰よりも努力をしていたのかもしれません。また「運」もあったのかもしれません。
だからどこかの自己啓発セミナーみたいに、「誰もが楽をして(例えば成功を心に想い描くだけで)何事もうまくいく」などと甘いことを言うつもりは全くありません。
ただ間違いなく言えることは、「神様は、金持ちにも貧乏人にも1日24時間という時間だけは平等に与えてくれた」というのと同じように「ひらめき」「創造力」も私たちに等しく与えられた能力であると言うことです。
ではなぜ、「自分に能力はない」と思ってしまうのか。
それは私たち自身が、限界(リミッター)を持ってしまう。あるいは「創造性」や「ひらめき」に自ら蓋をしてしまう、という特性も私たちにはあるからです。
その理由の一つが、私たちの「生存本能」が働き過ぎることです。
新しいこと、今までに誰もやったことのないことというのは「危険」を伴います。
誰も食べたことがない動物や植物を口にする。まだ誰も行ったことがない未踏の地に足を踏み入れる。空を飛ぶ、宇宙に行くなど誰もがやったことがないことを成し遂げる。
人類の歴史を見れば、このような挑戦者(ファーストペンギン)が私たちの可能性を広げ、イノベーションを起こして、人類の発展に寄与してきましたが、その挑戦の過程で、多くの命が失われてきたことも事実です。
「生き延びる」ことを第一に考えれば、何かを創造しようとか、イノベーションを起こそうとか考えず、目上(親や先生や上司など)の人には従い、前例を踏襲し、決められたことだけをやる。
「安全」は私たちがもっとも大事にしていること。これもまた生き延びる一つの知恵なのは間違いない。
だから「挑戦したいという気持ち」「新しいものを創りたいという気持ち」を抑えることを批判するとか、間違っているというつもりはありません。
ただ、意識しているうちはまだ良いのですが、そうしているうちに、私たち自身がそのリミッターの存在、蓋の存在に気が付かなくなってしまった。自分自身が一生懸命「ひらめき」「創造性」にブレーキをかけていることに、気づいてあげても良いんじゃないでしょうか?

VUCAの時代、変わらないものも滅びる
しかしこれも行き過ぎると、必要な時に変わることができない、という弊害も起こります。
環境に順応しすぎると、その環境が変わったときに必要な対応ができなくなる。
ジュラ紀の温暖な環境に適応しすぎて巨大化した恐竜たちが、隕石の落下による環境変化であっさり滅んでしまったように、「変化できないものは滅びる」のもまた事実です。
私たちは常に現状維持と変化の間で揺れ動いています。
前提が変われば「正しいこと」も変わる。目的に応じて行動も変える。普段は現状維持のための行動をしていてもいい。
でも「いざ鎌倉!」というときは行動も考え方も柔軟に変える。
先が見えないVUCAの時代にはそういう姿勢が求められます。
この本を書いた目的は、決して限界(リミッター)をいつも外しましょうとか、蓋を開けっぱなしにしましょうと言うことではありません。
自分が自分で設定しているリミッターや蓋の存在に気づいてあげることで、必要なときにそれを操作する。ちょっとだけ蓋を開けるとか、リミッターのレベルを上げるとか、そういうことをするお手伝いをしたいと思いました。
そしてその方法をできるだけ具体的に示すことで、だれもが「必要なときにひらめくことができる」ようなメソッド(方法論)を示す。(具体的には「4つのプロセス」で誰もがひらめきができる手法を示しています。)
是非ご一読くださいませ。