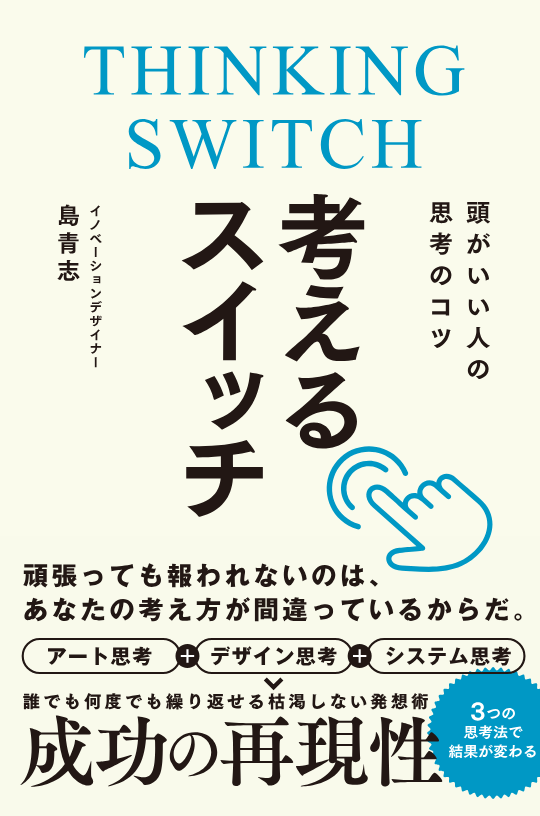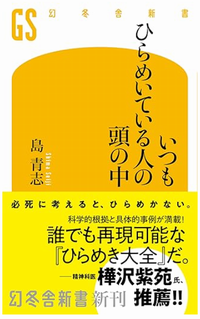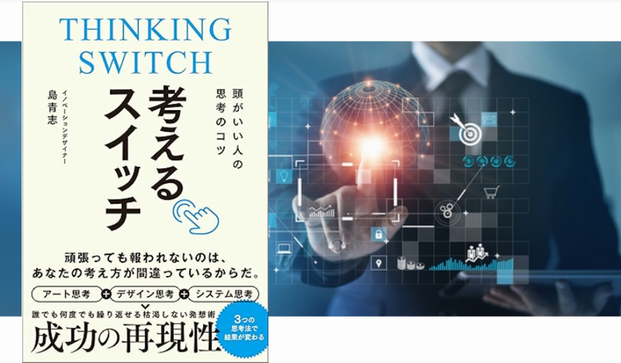
明らかにバブルな今のAI環境
AIの進化が凄まじいです。
ChatGPTを筆頭とした生成AIの性能の進化はおそらく皆さんも実感していると思います。
そして金融(株)の世界はもっと凄まじい。今年(特に4月以降)の日米の株価が上がっていますが、米国のS&P500のなんと4割が、AI銘柄の7社(Google、Amazon、Meta、Apple、Microsoft、Nvidia、Tesla)が占めています。日本に至っては直近の株価上昇の半分をたったの3社(ソフトバンク、アドバンテスト、東京エレクトロン)で押し上げています。もちろんどれもAI銘柄ですね。
明らかにバブル状況。
そうやって集まった資金で、これらの会社は数十億兆ドルという国家予算並みの投資を継続中で、それがAIの性能の進歩を促し、更にお金が集まるという「フィードバックループ」を形成しています。
ほんの1~2年前には、「生成AIを仕事や教育現場に導入すべきか」という議論がありましたが、今では使うのは前提、当たり前で「どう使うのか」「どのように活用するべきか」という次元の話になっています。
生成AIが登場して、まだ3年足らず。ブームになってから数えればまだ2年程度にしか経っていません。
それを思えば、これからの数年間、あるいはその先、AIがどれほどの進歩を見せるのか、想像するのも難しそうです。
AIにもある限界
しかしもちろんAIにも限界があるのも事実。
たとえば物事の優先順位をつけること。
「AIにはできないのですか?」という疑問の声が聴こえてきそうです。
自分にとって何が優先事項で何がそうでないのか。
これは自分にしか判断はできません。
もちろんルーティンワークのような、「過去の基準」で決められるものでしたら、その
「基準」を教えたり学習させることによって優先順位をAIが示すことができます。
しかし、初めてのこと、まだやったことがないことは、もちろんAIにもわかりません。
そのためには、「論理」だけでなく「感情」「感性」が必要だからです
拙著の「考えるスイッチ」で、脳が傷ついて感情が無くなったビジネスパースンが、
まったく優先順位がつけられなくなった事例を紹介しました。
彼は仕事だけでなく、日常生活も上手く遅れず家庭も崩壊してしまいました。
このようにAIの能力は意外と「狭い」のです。
また最近のAI研究でも、大規模言語モデルの規模よりも、人間による「ファインチューニング」が生成AIの性能の善し悪しに影響を与えていることがわかってきました。
この根本原因は、現在のAIは、推論はできるけど考える。思考することができないということにあります。
生成AIに接していると、「AIも(私たちのように」考えている」と思いたくなりますが、実は「推論」しているだけです。
(これを最近の研究では「ポチョムキン理解」と呼んでいます。詳しくは「考えるスイッチ」の第6章をご参照ください)
推論を簡単に言えば、1,2と数字が続けば次は3だろうと予測すること。もちろんこんなことは、AIでなくExcelでもできるわけですが、だからといってExcelが思考していると思う人はいないわけです。
もちろん、AIはこの推論の性能がすごいので、一見複雑そうな問題でも、見事に(人間より早く正確に)行うことができるのですね。
もっと言えば、こういった推論は、犬や猫などの「動物」もできます。人の言うことを聞けば褒めてもらえたり、食べ物ももらえる。彼らはそれがわかっている(推論できる)ので、私たちは「賢い」と可愛がるのですね。
つまり人間は、「考える」「思考する」ことができる唯一無二の存在であるということ。

思考しない人が増えている
しかし最近周りを見渡すと、あるいは自分自身も鑑みると、「考えない」「思考しない」人が増えている気がします。
あるいは自分にも言えますが、「思考する」「考える」ことが減っているのではないか。
「人から言われた(教えられた)ことをする」「周りの風潮に合わせる」これは「思考」ではありません。なぜなら動物だってAIだってできるからです。
そして、私が、今のAIの進化を見ていて、最も危惧しているのが、「人間の方がAIに頼りすぎて、ますます「考えなくなってしまう」こと」です。
「AIの判断を人間が全てうのみにしてその通り判断してしまう」そんなことが増えているんじゃないでしょうか。
「AIの進化」が問題と言うより、「人間の退化」のほうが、遥かに問題じゃないかと思います。
今、スマホ依存が問題になってきていますが、これからはAI依存が問題になってくる。
「考えない人間」が増えて来るんじゃないかと思います。
これはスマホ依存よりもっと悪い結果をもたらしそうで怖いです。
だからこそ、「考える」「思考する」とはどういうことか。
そんなことから「考えるスイッチ」という本を書いたのです。