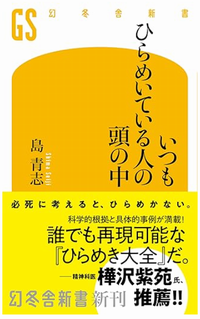アジャイル・ガバナンスとは
昨年(2021年)暮れ12月24日、「デジタル社会の形成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画について」が閣議決定されました。
このなかで、デジタル社会の実現に向けた構造改革のための5つの原則のひとつとして「アジャイル・ガバナンス原則」が定められています。
2016年の閣議決定で、我が国がこれから目指す社会を「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会)」と定め、Society5.0と名付けられました。
そのSociety5.0社会において、政府や企業、あるいは個人やコミュニティが行うガバナンス(統治・経営)のあり方について議論されてきたものが「アジャイル・ガバナンス」です。
Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会報告書(Ver.2)
経済産業省による2021年7月の報告書「Governance Innovation vol.2」によれば、「アジャイル・ガバナンス」とは、政府、企業、個人・コミュニティといった様々なステークホルダーが、自らの置かれた社会的状況を継続的に分析し、目指すゴールを設定した上で、それを実現するためのシステムや法規制、市場、インフラといった様々なガバナンスシステムをデザインし、その結果を対話に基づき継続的に評価し改善していくモデルである。」と定められています。
従来の「ガバナンス(統治・経営)」は、基本的に一人あるいは複数の「権力者」がいて、この権力者がルールを定め、他の人はそのルールに従うという構造で成り立っていました。(これは民主制も独裁制も同じで、権力者自身もルールに従うのが民主制、ルールの外なのが独裁制です。)
社会が変化すれば、それに応じてルールを変えていく必要がありますが、当然法改正などのルール改正は、社会の変化の後追いになります。
これは、社会の変化を抑える、つまり秩序や社会の安定を保つ効果があり、必ずしも悪いばかりではありません。
しかし現代ほど先が読めない時代では、このようなやり方は、社会の変化への対応ができないため、イノベーションを阻害し、日本の国力を下げる結果となっています。またSociety5.0の社会では、人だけでなくAIも行為者となり、例えば自動運転車の事故の責任問題など、今までの法体系、統治体系では適応できない事例もでてきます。
企業統治やビジネスデザインにおいても「責任者=権力者」という構造が崩れて、完全フラットな自律組織となったら、なにか問題が起きた場合、誰が「責任を取る」のか、今のガバナンスの仕組みではうまく機能しないことも明らかだと思います。
Governance Innovationとアジャイル・ガバナンス
経済産業省の「Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会」は2019年からスタートし、2020年に「Governance Innovation vol.1 ~ Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン ~」そして、2021年「Governance Innovation vol.2 ~ アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて ~」が発行されました。
vol.1では、「国家が一律にルールを定め、監督・執行を行うモデルではなく、ステークホルダー間の水平的な関係を重視した、柔軟なガバナンスモデルが必要になってきている」と述べられています。
つまり今までのような「完全な理性を有する無謬な国家が、均質な市民を垂直的に統治するモデル」は、変化が速く将来の予測が極めて困難になっている現代においては、そのような無謬な統治主体として国家を想定することは困難であり、「国家とステークホルダーとの関係が水平化しつつある現状を踏まえ、ステークホルダー自身による情報提供や自己監督・自主改革を引き出すために制裁権力を活用するという、新たなガバナンスモデルへの移行が望ましい」とされました。

新たな社会では、国家や政府が頂点に立ってガバナンスを行うのではなく、国家・政府、企業そして個人・コミュニティが下図のような、積極的な役割を担っていく形(アーキテクチャ)となります。

そしてその統治者(国家、企業、個人)が具体的にどのようにガバナンス(統治・経営)を行っていくのかを定めたのが、vol.2の「アジャイル・ガバナンス」です。
なぜアジャイルなのかについて一応述べておくと、例えば企業も受動的ではなく、主体的そして自律的にガバナンスを行う必要があるからです。自分自身で自身を取り巻く環境や情勢を分析し、様々なステークホルダーと絶えず調整を図っていきながらビジネスをデザインする。これはアジャイルなやり方が不可欠なためです。
報告書ではアジャイル・ガバナンスについて、「『環境・リスク分析』『ゴール設定』『システムデザイン』『運用』『評価』『改善』といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていくガバナンスモデル」と定めています。
具体的には下図のような形になります。

アジャイル・ガバナンスでの生き方とビジネスモデルデザイン
アジャイル・ガバナンスの元では、国家や企業だけでなく、私たち個人も一人ひとりがゴールを定め自律的にサイクルを回していく必要があります。
法体系も今までは、「ルールベース」つまり国家などが細かくルールを定め、私たちはそれに従って違反しないように行動すれば良かった。逆に言えば法に違反しない限り何をしても良いということですし、企業で言えば所有者(株主)がいかに儲けるかだけ考えればよかった。
しかし、アジャイル・ガバナンスでは国や政府は今までのようにルールを作って従わせるという存在ではない。
それぞれが、「ゴールベース」で物事を考えルール(法や規則や標準あるいは行動規範など)をそれぞれのステークホルダーと定めていかなければならないのです。
企業は「ステークホルダー資本主義」的に行動していかなければなりません。SDGsやESGも「お題目」「建前」ではすまなくなります。
そういう中で、私たち一人ひとりのゴールとはなにか。これは「なぜ働くのか」「どう生きるのか」つまり私たちが自分の存在意義を問い、それを発信することで、これはまさにアート思考(Art)であり、それをアジャイル(Agility)で回しつつ、自律的(Autonomy)に周りの人(ステークホルダー)と協働する。「3つのA」の追求しつつビジネスをデザインすることがアジャイル・ガバナンスの鍵となりそうです。

具体的にアジャイルをどう回していくか、特に、アジャイル・ガバナンス・サイクルの「システムデザイン」をどのようなフレームワークで創出していくかということについて、私たちのビジネスデザイン(ICONIX for Business Design)はひとつのソリューションを提供していると思います。
昨年秋の日本能率協会主催の「DX時代に求められる「3つの思考法」入門セミナー」では、弊社講師が「ワクチン政策」について、様々なステークホルダーと協働して円滑にすすめるモデルのワークショップを行いました。

ビジネスモデルデザインで「ワクチン政策のシステムデザイン」のワークショップ
![]()
ICONIX for Business Design
日本能率協会主催「DX時代に求められる「3つの思考法」入門セミナー」開催