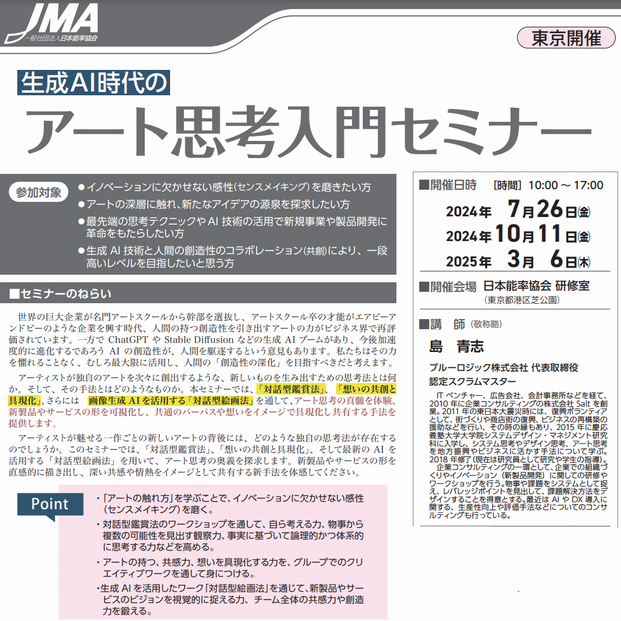アート思考は19世紀の英国で始まった
先日(10月15日)の日経新聞で「ビジネスのアート思考後押し 欧州機関『持続可能探る』という記事がありました。
ここではアート思考について、
「定義を考える場合『デザイン思考』との対比が分かりやすい。両者は主体となるものが異なっている。デザイン思考は顧客のニーズが主体で、それに合わせて課題解決を示す。一方、ファクトやデータでなく、まず感性や直感で欲しいものや望む未来を描くアート思考は、顧客やユーザーが想像もしない戦略を打ち出せる可能性があるとしてビジネスでも注目されている」
と説明されており、三菱地所やZOZO、NTTなど様々な企業の取組が紹介されています。

日経新聞2022年10月15日朝刊
このようにここ数年ビジネスの世界で注目を集めているアート思考ですが、この考え方は必ずしも新しいものではなく、実は19世紀のイギリスでも広がりをみせた思想です。
当時のイギリスと現代の日本を対比することで、「なぜ、今アートやアート思考に注目が集まるのか。この思考はどのようにビジネスや、それに携わる人々の幸福に繋がるのか」も見えてくるかもしれません。
アート思考の源流ウィリアム・モリス
「アート思考」と呼ばれるこの思考や思想はどのように生まれたのでしょうか。
もちろんまだ定説があるわけではないのですが、私は、今から150年ほど前のイギリスで、小説家・詩人・建築デザイナーそしてユートピア社会主義者など様々な顔を持つ、ウィリアム・モリスを源流と考えています。

ウィリアム・モリスの代表作:内装用ファブリック《いちご泥棒》1883年
(https://www.william-morris.jp/)
19世紀のイギリスは産業革命の発祥国として世界をリードしていましたが、アメリカやドイツなどの台頭による地位低下、労働問題や環境問題など「資本主義の矛盾」が表面化しつつあった時代でした。
生産工程の機械化によって大量生産が可能となり、画一的で効率重視の製品が世の中に溢れました。
しかしそれまで「職人」が担ってきた仕事は、安い賃金の「労働者」に置き換わり、彼らを使用する資本家と呼ばれる人たちに「富」は集中します。
仕事(労働)とは、その「資本家」やその代理人である「使用者」から命じられたことをそのとおりに作ること。仕事とは賃金をもらう手段であり、生きるためのものとなりました。
この状況をモリスは、「人は機械の奴隷」と述べ、「人間とは生きるために働き、働くために生きる存在でしかない。職人や、自由意志でものを作る人間の役割はもう終わったのだ」と嘆いたのです。
産業革命以前も様々な抑圧や不合理なことは多かったものの、仕事そのものに関して言えば、職人は自由なものづくりができました。
モリスは「職人は可能な限り自分が楽しくなるように仕事をした。美しいものを作ることは彼らの喜びであって苦しみではなかった。しかし、産業革命以降の機械工たちは、効率や利益重視のため、一秒たりとも芸術に浪費することが許されない。現体制は、労働者に芸術を作ることを許さない」と述べています。
このような状況でモリスはアートと仕事の不可分性を訴え、「Art is man’s expression of his joy in labour.(アートとは、人が仕事に対する喜びを表現することである。)」と唱えたのです。
モリスは、アートを生み出す仕事というものは自発的なものであり、自分がその仕事をするのが楽しいから、さらにその仕事の成果(製品やサービスなど)に触れた人に喜びを与えるものを生み出すという希望のために行なわれるものと考えました。
そして、こうしたアートの生産、およびその結果である仕事における喜びは、絵画や彫刻などのアート作品の製作だけにあるのではなく、すべての仕事の重要な一部であるとしたのです。
これは上記のアート思考の考え方「ファクトやデータでなく、まず感性や直感で欲しいものや望む未来を描く」とほぼ同じと言っても良いと思います。

モリスのレッドハウス(住居兼工房)
現代の日本との共通点
翻って現代の日本を取り巻く環境を考えてみたいと思います。
20世紀は1911年に刊行されたフレデリック・テイラーの「科学的管理法」から始まって、効率化や分業化がより一層進んだ世紀でした。その中で最も成功した国の一つが日本であるのは間違いないでしょう。
しかし、20世紀型経済が、社会主義、資本主義とも行き詰まる中、「機械の奴隷」は「FA(ファクトリーオートメーション)」や「IT」「コンピュータ」の奴隷にとって代わり、効率化も極限に達しますが、そこから次の策が打てません。
追い上げてきたアジア諸国との優位性もなくなり、「輸出で稼ぐ」モデルもほとんど崩壊しました。
「ブラック企業」が流行語になる中、「働く喜び(joy in labor)」はますます遠くなった感があります。
これは産業革命が極限に達した19世紀のイギリスと同じような状況といえないでしょうか。
モリスのアート思考の実践
モリスは、思想家であると同時に実践家でもありました。
社会主義運動に身を投じると共に、「ユートピアだより」などの著作で「理想の未来の姿」を描きました。
「ユートピアだより」は、日本で最初に紹介されたモリスの著作ですが、貨幣も所有権の概念もなくなった22世紀のイギリスの姿を描いた小説です。
人々は「生きるため」ではなく、「好きなこと」「やりたいこと」を仕事にしています。「仕事の目標」もないので技術もそれほど発展しませんが、自分や周囲の人達がほしいと思うものをそれぞれが創り合っています。
所有の概念がないので、「財産権の争い」「富を独占しようという競争」もないのですが、各々のこだわりや美的感覚を大事にしているので、街は清潔でセンスが良く、簡素ながらも美味しい食もたくさんあります。
アートと仕事が一体となったモリスの理想の世界。読んでいてそれほど「実現不可能」とも思えなくなってくる不思議な感覚になります。(ジェームズ・ホーガンのSF小説「断絶への航海」と通じるテイストを感じました。)

ウィリアム・モリス「ユートピアだより」岩波文庫
そしてモリスは実践の場として、モリス商会を設立して、職人仕事にこだわりつつ数々の美しいインテリア製品やステンドグラスなどを作り出しました。
生活と仕事、アートを一致させようとするモリスの思想とその実践は、「アーツ・アンド・クラフツ運動」として世界に広がって、20世紀のモダンデザインの源流となり、またドイツのバウハウス、日本でも柳宗悦の民藝運動や宮沢賢治の(イーハトーブの世界の実現を目指した)羅須地人協会の活動にも影響を与えたと言われています。
アートの目的は幸福の増大
モリスは、「芸術(アート)の目的は、仕事を、私達の衝動が楽しく満足できるものにして、作る価値のある物を作っているのだという希望をこの精力に与えることによって、労働の呪いを破壊することである」と述べています。
そして「芸術を生み出す労働は自発的なものであり、一つには労働それ自身のために、一つにはそれを用いる人に喜びを与えるものを生み出すという希望のために行なわれる。こうした芸術の生産、およびその結果である仕事における喜びは、絵画や彫刻などの芸術作品の製作だけにあるのではなく、他のすべての労働の一部をなしている」と述べ、芸術の目的は「人間の幸福を増大させることである」と結論付けています。
仕事を通じて幸福を増大させること。幸福になるために仕事を行うこと。これが芸術(アート)そしてアート思考の目的といえるのではないでしょうか。